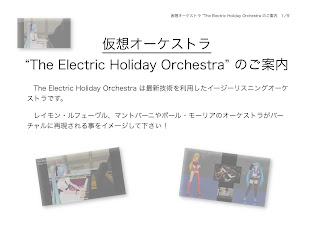で、例によってあちこちプレゼンしたけど、イマイチ効果は期待できず。 それでもそんな中、2017年に紹介されてた人が2018年にチョコっと手伝ってくれて、フミカの 3D データとビューアーを作ってくれる事になりました。 最初はプログラマーの人がチョイと趣味で作ってみました、みたいな感じで、スマホをターゲットに向けるとピアノを弾く初音ミクが現れるというシカケ。 これが2018年6月初旬の話。渋谷のカルチャーカルチャーのイベントにゲストで出た時、偶然連絡があり、ビューアーの簡単なテストが出来たので渋谷あたりで、っていう事だったので、イベントの準備中に持って来てもらって見たのが、この動画です。 ここでは一台のスマホにターゲットになる絵を表示しといて、そこにビューアープログラムを向けてカメラで見ると、そのターゲットのスマホの上にピアノを弾く初音ミクが浮き上がってきます。 ターゲットの絵は、この動画ではスマホを使ってるけど、別に印刷物でも、立体物でも OK です。 というわけで動画。